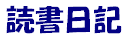
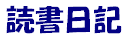
| 2005年 | 12月 |
| 2006年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2007年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| ←前月 | 2日 | アンチ「速読」
【遅読のすすめ】山村修(新潮社) |
次月→ |
| 3日 | 推理小説とは呼べそうにないのだが
【アルキメデスは手を汚さない】小峰元(講談社文庫) |
||
| 4日 | 主人公に共感できるかどうかがカギ
【ひとり日和】青山七恵(河出書房新社) |
||
| 11日 | 久しぶりにじっくり読んだ
【プラネタリウムのふたご】いしいしんじ(講談社文庫) |
||
| 15日 | 書評を読む
【へそまがり読書王】安原顕(双葉社) |
||
| 18日 | 一気に読んだけど、最後で・・・・
【風の谷のナウシカ】宮崎駿(徳間書店) |
|
アンチ「速読」 図書館の「図書」のコーナー(書誌やったかなあ。図書館というのもいっしょになってたかも)には、本についての本がいっぱいある。多いのは「速読法」とか「1分間に10ページ」とか「こうやって○○冊読む」とかである。現代人は時間がないのに、読まなければならない本は増える一方なのだろうナア。なにしろ世の中、情報化社会である(死語だ)。どれだけの情報を蓄えておけるかというのが勝負になるのだ。そのためには、如何に他人より短時間に多くの情報を得ることができるか、というのが大事なのだ。 ホンマか? それがそんなに大事なことなのだろうか? ゆっくり読まないと分からないこともある。読み飛ばして、その本の一番重要な、一番味わい深い部分を味あわずに終わっている。そんな読み方をしていませんか? している。確かにしている。読み飛ばしているところ、いっぱいあるなあ。そして「面白かったからもう一回読もう」なんてことはほとんどない。あるとしたら「前に読んだけど、忘れてしもたから、もう一回読んでみよ」ということぐらい。 著者に言わせると、速読術の「大事な部分をおとさず読む」というのは「読書」とは呼べないのだそうだ。文章を味わってこその読書。確かにそのとおりです。 それにしても。数ある読書案内で、「ゆっくり読みましょう」というのはこの本ぐらいであった。アンチ好きにはたまらん本であったよ。みんな読め。時間をかけて。 推理小説とは呼べそうにないのだが 1973年江戸川乱歩賞受賞作「アルキメデスは手を汚さない」を読んだ。今頃になって。話題になったころは読む気にならへんかったなあ。話題になってるものほど読みたくないっていうひねくれ者だったのだ。いまでもひねくれてるけど。 で、それから30数年。今読んでみると、これって推理小説のようで推理小説でないのだね。べんべん。舞台は高校。しかも豊中ですと。 と、なにやら謎が謎を呼ぶような、探偵小説の王道を行くようで・・・・全然行かないのだなあ。 そして、最初に書いたように舞台は豊中なのだが、ほとんどが標準語で話が進むため、高校生の描写などを読んでいると、そこが大阪ではなく東京のような錯覚をおぼえてしまう。まあ、場所はどこでもよかったんやろけど。というぐらいの、地理に関係ない話の展開でありました。 江戸川乱歩賞受賞、とかいう肩書から想像すると、ちょっと肩透かしを食らうかも。あ、ちゃんとトリックらしいものもありますよ。 主人公に共感できるかどうかがカギ 2007年芥川賞受賞作、「ひとり日和」を読んだ。 まあなんというか。こういうのが芥川賞かあ。まあ選考委員を考えたら、こんなものなのかなあ。いや、でも金原ひとみや綿矢りさはおもしろかったよ。それにくらべるとなあ。 なにしろ、主人公の(ということは語り手の)「わたし」に、まったく共感を持てないからなのだな。コンパニオン(パーティーなどの)のアルバイトなどをして日銭を稼ぎ、昼間も空いているからと駅の販売所で働き、駅員と恋をする。その恋も、ほのぼのとは程遠い感覚。というか、「ほのぼの」を頭から否定しているような。 正直言って、こんな女とは知り合いにもなりたくない。めんどくさそうやし。うだうだと自分の話を(自慢話ではない)して、そのあげくに どんな小説でも、その登場人物に共感できないと、読んでいて居心地が悪いものだ。人間はひととおりではないし、いろんな面を持っているから、どこかに共感できる面があるもんなんだろうけれど、今回のこれはあかんかったなあ。 久しぶりにじっくり読んだ いしいしんじって、どういう人か全然知らなかったのだが、図書館で「プラネタリウムのふたご」というのを見て、本の題名がなかなかいいなあと思って読んでみたら、これがほんとに素晴らしかった。久しぶりに、読み飛ばすことなく、楽しくじっくり読んだよ。おかげで読むのに時間がかかったけど。 村のプラネタリウムでみつかった双子の兄弟。プラネタリウムの解説員「泣き男」に引き取られ、テンペルタットル星にちなんでテンペルとタットルと名付けられる。 なんていう説明は、どうもこの話の本当の面白さを伝えてなくて。どうしようかなあ。 まあ文章だけよかっても、なかみがなってなかったら読む気にならんもんですが、中身もとてもよく出来ていて。いや、文庫にして500ページにもなるんやけど、ほんまに構成とか、話の進め方とかがよくできていて、最後まで楽しく読まされたよ。「最後までワクワク」とか「最後までハラハラ」とかはよくあるけど、「最後まで楽しく」っていうのは、これはもうほとんど古典のものしか記憶がないかなあ。 書評を読む 書評を読むのが好きだ。新聞の書評欄も必ず目を通す。毎週日曜日が書評がたくさん載る日なので、新聞を読むのも時間がかかったりするくらい。 というわけで、一番手っ取り早いのは書評である。書評にはかいつまんだその本の内容、著者の傾向、今までどんな本を書いたか、等々、「その本を読んで楽しいか」という目安になることが書いてある。これを目安にして、読みたい本を探すのだな。 ここで大事なのが、評している人と自分の性格、嗜好が似通っているということである。当然のようでこれがなかなか難しい。評者とは会ったこともなければ話を聞いたことさえない人だっている(マスコミに出てこない人が多いような気がする)。だからどの人が自分と性格が合うか、意見が合うか。それを探るためにその人が評した本を一度読んでみて、それでその人の評価どおりだと自分が思ったら、その人と自分の嗜好は同様だとわかって、それからはそのひとの「書評」を信用してもいいわけである。 と、前置きが長くなったけれど。安原顕は、どうやら信用してもいいようだ。と書くとちょっと誤解もされそうやけど。「へそまがり読書王」は2001年に書かれた書評が多くを占めている。あの年。9.11があった年だ。そういう世俗の出来事は文学に関係ない、という時代では今はないのだな。安原顕というひとは、そうとうな読書家で(月に100冊は読むらしい)、その上独特の自説を展開しもする。「天皇は戦争責任をとるべきだった」「宗教がなくならない限り世界に紛争は絶えない」「そんな人類には絶望している」等々。 で、そういうバックボーンは有りつつ、書評は書評としてしっかりと書かれているのですな。よいものはよい。あたりまえやけど。その本の「ここが気に入らない」「ここがいい」「ここんところが惜しいんだよね」と、はっきりと書かれていて、ああ、これはよくあるヨイショ記事とは違うなあ、信用できるなあ、と思うのであるな。 と、えらそうに書いてるけど、半分ぐらい読んだところで挫折した(分厚い本なのです) 「読者は踊る」を読むと、斎藤美奈子は安原顕と比べると、もっと口調がはっきりしているし、本の裏側というか、著者の思想・思考の矛盾まで読みとってしまって、こりゃ上には上がおるもんやなあと思ってしまった。 さらに、先に書いた「自分の嗜好に合う書評」というのにつながるのだけれど(というか、コレを読んだから上の文章が思い浮かんだのかも。パクリか、わし) さて、この本が書かれたのは1996〜1998年。その時代に出版された、話題になった本を取り上げているので、今読むと一層面白い。 そういう、素直な目で、しかしときに辛辣な評を書くところがとても僕の好みに合っている。こういう人、居たなあ、と思い出した。ナンシー関だ。 それにしても。ここに載っている「環境ホルモン」とか「利己的遺伝子」とか「複雑系」とか、そういう本はどこに行ったんでしょうねえ(それぞれの章の最後にちょこっと、それらが消えた理由も伺える考察がある) 北尾トロというひとはよく知らない。「出版業界裏口入学」は、出版会の裏側を暴いた暴露本、ではなく(ごめんなさい)、一般常識として読書好きに信用されていることがら、あるいは「読書好きならこういうことは知ってるだろう」と一般人に思われていることは、「本当はどうなんだろう」ということを、実地で調査した本である。といっても、その言い回しでも分かるように、それを楽しんで、つまりは「なんちゃって」というところを含んだ調査なのだが。 「国立国会図書館の使い方」とか「サイババに会いに」(ほんとにインドに行ってきた)とか「イヌ・ネコ本の決定版」とか(ちょっとうろ覚え)。 一気に読んだけど、最後は・・・・ 図書館に1〜4巻をリクエストしたら、全7巻をいっぺんに用意してくれて。まあしゃあないかと思って、全部借りてきました。 |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
